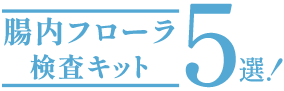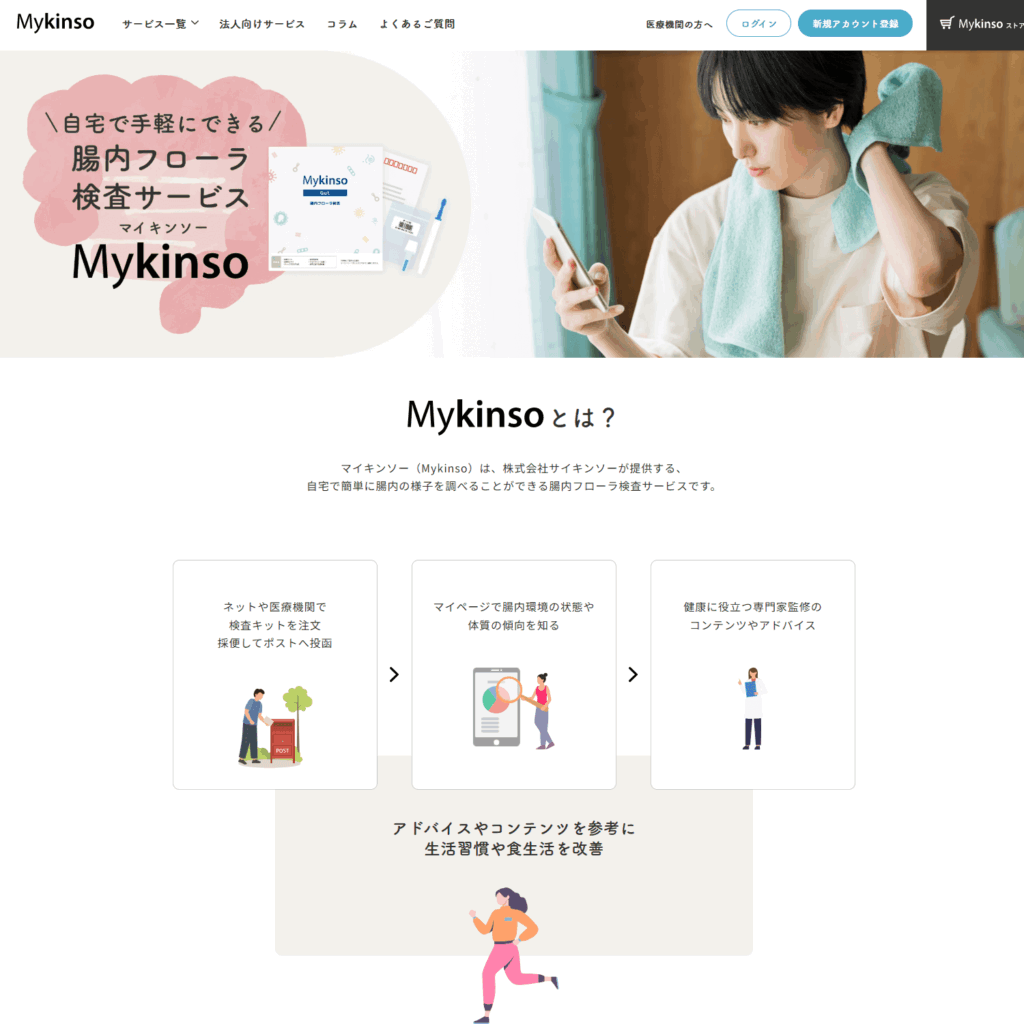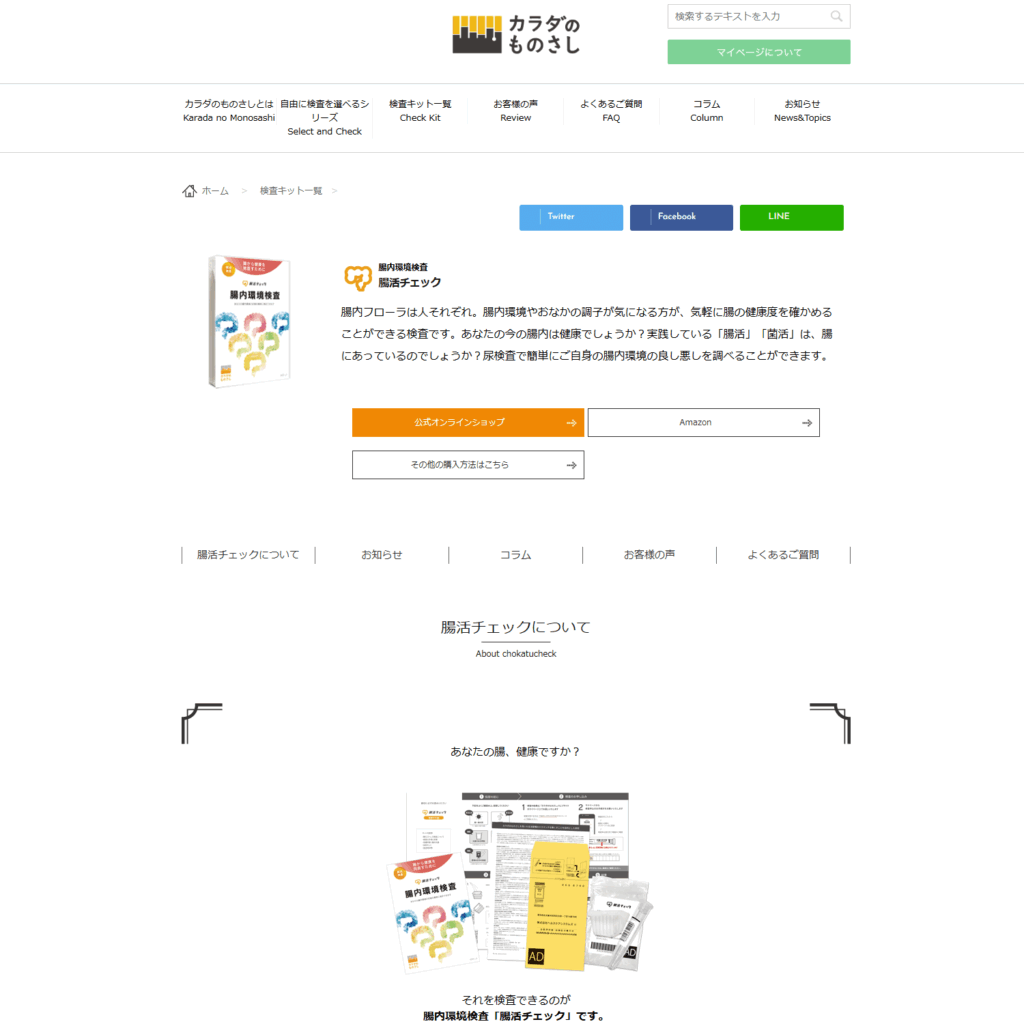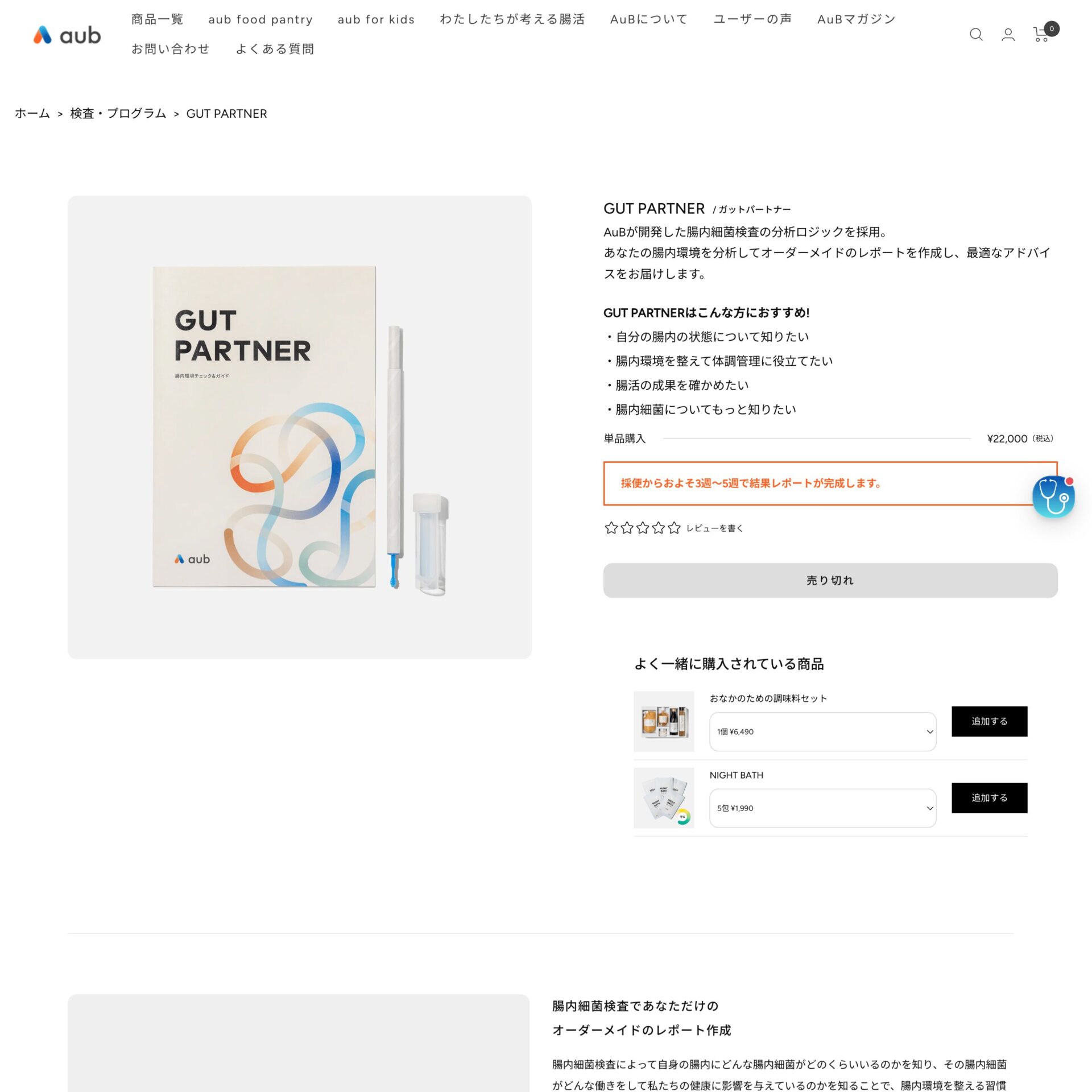数々の研究から、腸内フローラの乱れは肥満との関連性があるということが報告されています。本記事では、腸内フローラの乱れが肥満を引き起こすメカニズムを解説し、日本人特有の腸内フローラと肥満リスクの関係について紹介しています。腸内環境を改善して肥満を予防する方法についても触れているため、肥満が気になる人はぜひご一読ください。
CONTENTS
腸内フローラとは?
人の腸内には約100兆個を超える数の細菌が棲み着いており、約1000種類以上の細菌たちが種類ごとに腸内の壁に集団をつくっています。その様子がまるで花畑のように見えることにより、腸内に群生する腸内細菌叢を「腸内フローラ」と呼ぶようになりました。
腸内フローラの乱れは便秘や下痢だけでなく、アレルギーやうつなどさまざまな健康問題につながる可能性があり、健康維持のために腸内フローラを整える腸活が注目されています。
腸内フローラと肥満の関係
腸内フローラは、肥満にも関係しているといわれています。腸内細菌がいないマウスに、肥満の人から腸内細菌叢を移植する実験において、そのマウスが肥満化したという結果が報告されました。
この研究では、肥満の人の腸内にはファーミキューテス門に属する細菌が多く、一方でバクテロイデーテス門に属する細菌が少ないということも分かっています。ファーミキューテス門とバクテロイデーテス門の比率を表す数値をF/B比と呼び、世界的にはF/B比が高い人ほど肥満になりやすい傾向にあるというのが定説です。
日本人の腸内フローラの特徴と肥満リスク
ただし、日本人については、F/B比と肥満を単純に結びつけられないという研究報告が発表されています。日本人を対象とした調査では、F/B比の高さと肥満には相関関係が見られないことが報告されました。
また、国別に腸内細菌叢の特徴を比較した研究結果では、日本人の腸内細菌叢が他国とは違った特徴をもっていることが分かっています。明確な理由は明らかになっていませんが、日本独自の食文化や遺伝的な要素などによって、日本人は「F/B比が高い人は肥満の傾向がある」という定説に当てはまらないと考えられます。
腸内フローラの多様性と代謝への影響
研究では、腸内フローラに存在する細菌の多様性と、代謝の関係が注目されています。痩せている人の腸内細菌叢は細菌の種類が多い一方で、肥満の場合は細菌の種類がそもそも少ないという報告もあり、肥満を防ぐ細菌が少ないことにより太りやすくなっている可能性があるでしょう。
短鎖脂肪酸の減少が引き起こすエネルギーバランスの乱れ
肥満には、短鎖脂肪酸の減少も関係していると考えられます。脂肪酸の種類は、炭素数が12以上の長鎖脂肪酸、炭素数が7~11の中鎖脂肪酸、炭素数が6以下の短鎖脂肪酸の3パターンです。
短鎖脂肪酸は、体内でエネルギー源になるほか、腸内環境の改善や肥満の抑制、抗炎症作用などの働きをもっています。短鎖脂肪酸は、腸内細菌が食物繊維を代謝することで産生されるのが特徴です。
人の腸内で細菌がつくり出す短鎖脂肪酸には、酢酸やプロビオン酸、酪酸などの種類があります。短鎖脂肪酸は、肥満を抑制するブレーキ役としての役割が注目されている物質です。
人の体は、飢餓時に備えて脂肪細胞の働きで脂肪を蓄えるようになっており、そのままにしておくと余分なエネルギーが脂肪細胞によって溜め込まれ肥満につながります。短鎖脂肪酸には脂肪細胞の過剰な働きを抑える機能があり、この短鎖脂肪酸が減少するとエネルギーバランスが乱れ、肥満を引き起こしやすくなると考えられています。
炎症反応の活性化による肥満促進
肥満は、腸内フローラの乱れによる炎症反応によって引き起こされるということが、研究によって分かっています。どのようにして肥満が促進されるのか、そのメカニズムを見ていきましょう。
高カロリーや高脂肪の食べ物を摂ったとき、人の体内では脂肪を分解するために胆汁酸が多く分泌されます。すると、胆汁酸に強い腸内細菌が増殖して腸内フローラが乱れ、腸管バリア機能が低下します。
腸内フローラが乱れることによって炎症反応が起こるのは、腸管バリア機能の低下で腸管から毒素などが体内に侵入し、血流に乗って全身に広がるためです。全身で引き起こされるさまざまな炎症が、肥満を促進していると考えられています。
腸内環境の乱れと肥満に着目した研究では、海藻類などに含まれる食品成分を摂ることで特定の腸内細菌が増加し、体内の炎症を抑えて肥満を抑制できる可能性が示されました。
腸内環境を整えて肥満を予防・改善する方法
多くの研究から、肥満を予防するには腸内環境を整えることが重要であることが分かっています。腸内環境を改善したい場合、食事はもちろんのこと、運動や睡眠などの生活習慣をトータルで見直すことが大切です。
食生活の見直し:発酵食品と食物繊維の重要性
腸内環境を整えるために、発酵食品や食物繊維を積極的に摂りましょう。発酵食品に多く含まれる乳酸菌には、乳酸や酢酸をつくり出し、悪玉菌の増殖を抑えて腸内細菌のバランスを整える働きがあります。
発酵食品の代表的なものは、ヨーグルトや納豆、チーズ、ぬか漬け、キムチなどです。ひとつだけではなく豊富な種類の発酵食品を摂るようにして、さまざまな善玉菌を補給するとよいでしょう。
また、食物繊維はお通じをよくするほかに、善玉菌のエサとしての役割をもっています。腸内細菌は食物繊維をエサとして短鎖脂肪酸をつくり出し、短鎖脂肪酸の働きによって肥満の抑制につながると考えられています。
反対に、食物繊維の不足した食事を続けると短鎖脂肪酸は減少するため、食物繊維の多い食事を心がけましょう。食物繊維を多く含む食品は、野菜や果物、海藻、大豆などの豆製品、ナッツなどです。
腸内フローラを支える善玉菌サプリの活用
腸内細菌の割合は、一般的に善玉菌が20%、悪玉菌が10%、どちらにも属さない日和見菌と呼ばれる細菌が70%といわれています。日和見菌は善玉菌が優勢であれば問題ありませんが、悪玉菌が優勢な環境になると悪玉菌の見方をして、腸内フローラを乱します。
しかし、悪玉菌がまったくいないのが理想的というわけではありません。悪玉菌が存在しない環境では、善玉菌が働きを失い、食べ物の消化・吸収が正常に行われなくなります。
大切なのは悪玉菌を増やさず、なおかつ善玉菌を活性化させて、腸内フローラのバランスを保つことです。善玉菌は食品から摂れますが、食事だけでは不足しがちなため、善玉菌サプリメントを活用して摂取するとよいでしょう。
生活習慣の改善:適度な運動とストレス管理
腸内環境は、運動不足やストレスなどがきっかけで乱れてしまいます。食生活の改善だけでなく、適度な運動やストレス管理を行って、腸内フローラのバランスを保ちましょう。
軽い運動をすると腸の動きがよくなり、便通がうながされて腸内環境の改善につながります。運動はときどき行っても効果が薄いため、継続的に取り組むようにしましょう。
運動はウォーキングや軽いランニングなどを、無理のない範囲で続けるのがおすすめです。また、適度な運動はストレス解消にも有効です。1日20分くらい散歩するだけでも気分をリフレッシュできるため、ストレスが溜まっていると感じたら少し外を歩いてみましょう。
充分な睡眠が腸内環境に与える影響
充分な睡眠を取ると副交感神経が優位になって、腸の蠕動運動が活発になり、腸内環境を良好に保つことにつながります。睡眠時間が極端に少ないと、肥満になるリスクが高まるといわれているため、6時間以上を目安に睡眠を取るようにしましょう。
睡眠時間を確保するだけでなく、睡眠の質を高めることも重要です。就寝前はパソコンやスマホの画面を見ないようにして、リラックスして過ごしましょう。
就寝の2時間前には夕食を済ませておくことや夜食を控えることもポイントです。また、就寝前はぬるめの湯船にゆっくり浸かるようにすると、血行がよくなるとともに就寝時間に体の深部体温が低下し、寝つきのよさや深い睡眠につながります。
抗生物質の使用に注意する重要性
細菌感染症の治療に使われる抗生物質の薬は、適切に使用すれば有用ですが、場合によっては腸内フローラによくない影響をもたらすことがあります。抗生物質には複数の種類が存在し、薬によって腸内フローラへの影響は違います。
たとえば、リンコマイシン系の抗生物質であるクリンダマイシンは腸内にいる標的以外の細菌にも作用をおよぼし、腸内フローラのバランスを乱すのが特徴です。また、マクロライド系の抗生物質が小児に与える影響を調査した研究では、幼少期にマクロライド系抗生物質を使用することで、喘息や肥満のリスクが高くなることが示されています。
ただし、すべての抗生物質が腸内フローラに悪影響を与えるというわけではありません。リファマイシン系の抗生物質であるリファキシミンには、有害な細菌を抑えて有益な細菌を増加させる働きがあり、腸内フローラの乱れによって引き起こされる過敏性腸症候群の治療に有効だと報告されています。
抗生物質はむやみに使用すると腸内フローラのバランスが崩れる原因になるため、使用には注意が必要です。しかし、適切に使えば治療に有効な場合もあります。医師や薬剤師に相談しながら、適正な量と期間で抗生物質の薬を使用しましょう。
腸内フローラ検査で自分の腸内環境を知ろう
腸内フローラ検査とは、腸内に存在する細菌の構成やバランスを調べ、可視化できるサービスです。腸内フローラ検査を活用することには、自分の腸内環境を把握し、健康維持に役立てられるというメリットがあります。
腸内フローラ検査の種類と選び方
腸内フローラ検査の種類は、大きく分けて「病院で受けるもの」「人間ドックや健康診断で受けるもの」「自宅でできるもの」の3つです。
病院で検査を受けると、結果に対するカウンセリングが提供され、生活習慣の改善について指導を受けられるというメリットがあります。また、人間ドックや健康診断では、オプションとして腸内フローラ検査を選択可能です。
腸内フローラ検査は、専用のキットを購入すれば自宅でも行えます。病院や健診施設を利用しなくても手軽に検査ができるため、忙しくて時間がない人にもおすすめです。
自宅用の腸内フローラ検査キットは、さまざまなメーカーから販売されており、検査内容をよく確認してから選ぶようにしましょう。とくに「調べたい検査項目があるかどうか」「結果を通知するレポートの充実度」「対象年齢」は事前にしっかりチェックしてください。
検査結果を日常生活に活かす方法
検査の種類にもよりますが、腸内フローラ検査で分かるのは腸内細菌の構成・菌のバランスや多様性・腸内細菌のタイプといった項目です。さらに、検査結果に対して、特定の病気に関連するリスクや生活習慣のアドバイスなどが提供されます。
腸内フローラ検査で解析された情報は、自分の腸内環境を把握し、食生活や生活習慣を見直すきっかけになるでしょう。腸内フローラ検査を活用して腸内フローラのバランスを整え、健康な体づくりを目指しましょう。
まとめ
腸内フローラの乱れは肥満につながるリスクがあり、肥満を予防するためには食生活や生活習慣を整えて、腸内フローラのバランスを保つことが大切です。腸内フローラ検査で腸内細菌の傾向を知ることは、自分の健康状態を振り返る第一歩になるでしょう。肥満が気になり始めた人は、対策として腸内フローラ検査を活用してみてはいかがでしょうか。