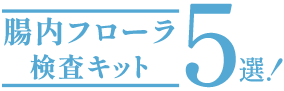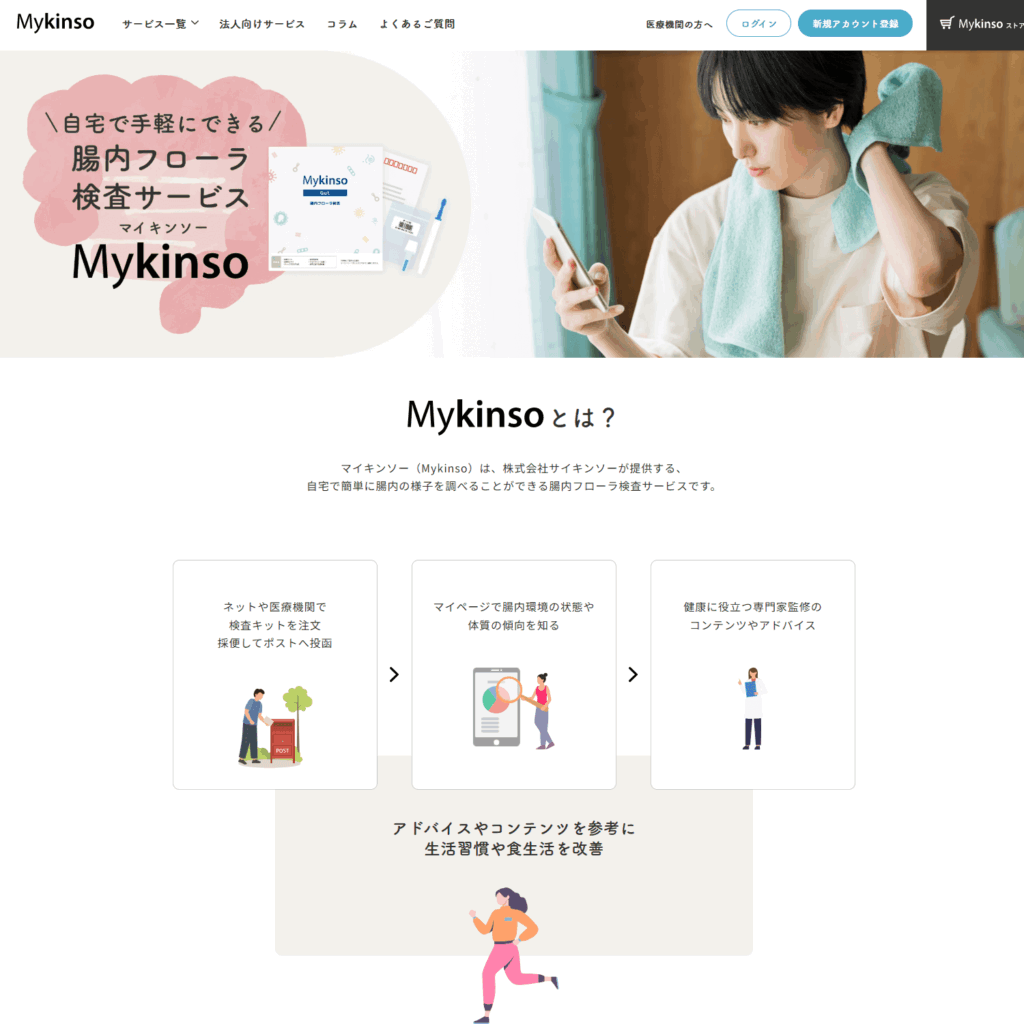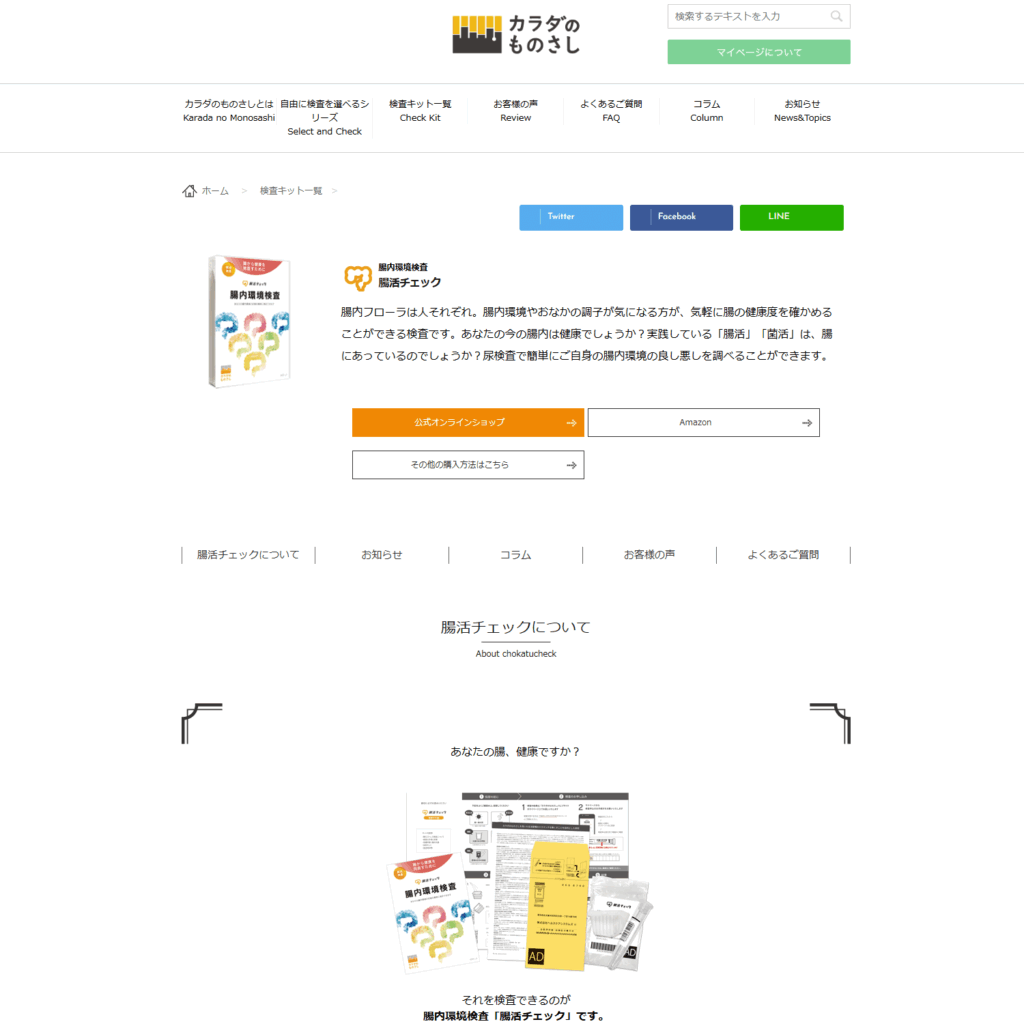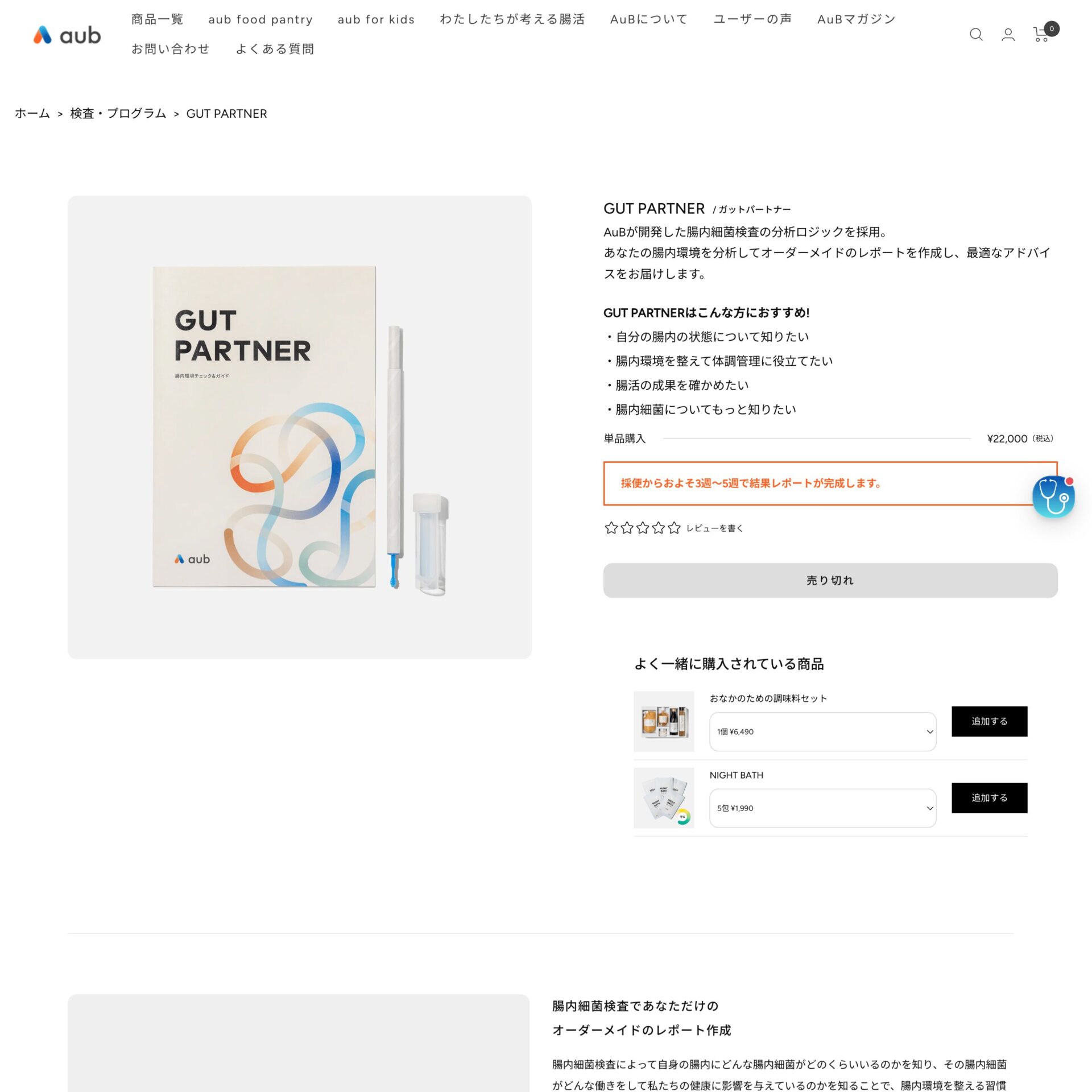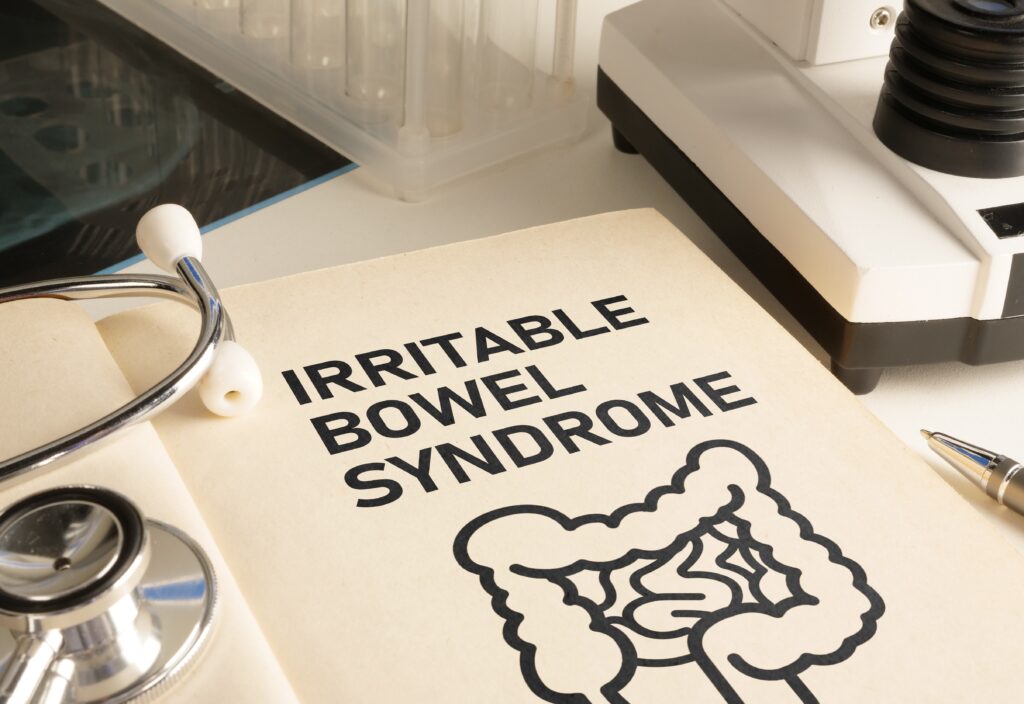
腸内フローラの状態が悪くなることは、過敏性腸症候群の原因のひとつと考えられています。この記事では、腸内フローラの乱れが過敏性腸症候群を引き起こす仕組みや症状の改善に向けた対処法について解説しています。
腸内フローラとは?その役割と健康への影響
腸内フローラは、人の腸内に存在する細菌叢のことを指します。人の腸内には約1,000種類の細菌が棲み、その数は100兆個に達するほどです。腸内細菌は種類ごとに腸内で集団をつくり、群生しています。これらの腸内細菌叢が腸内フローラと呼ばれるのは、その様が花畑に似ているためです。
腸内フローラは、人の健康に影響を与えることが分かっています。腸内に棲む細菌は、人が食べて消化できなかったものをエサとして代謝し、さまざまな物質を生成するのが特徴です。
腸内フローラにおいて腸内細菌から生成された物質は、腸から血管をとおして吸収され、全身へ運ばれます。その結果、腸内フローラは全身の健康状態に大きく影響をもたらすことになります。
腸内フローラと過敏性腸症候群の関係性を探る
慢性的な下痢や便秘、腹痛、お腹のガス溜まり、緊張時にお腹の調子が崩れやすいなどの症状がある場合、過敏性腸症候群(IBS)に該当する可能性があるでしょう。過敏性腸症候群は、腸内フローラの状態と関連性があるといわれています。
過敏性腸症候群の特徴
過敏性腸症候群は、腸そのものに異常が見られない一方で、便通の異常や腹痛などの症状が慢性的に起こる疾患です。下痢型・便秘型・混合型・分類不能型の4タイプが存在し、日本人の約10%がこれらの症状に悩まされているという報告もあります。
過敏性腸症候群にかかると急な腹痛や便意をもよおすことが多く、外出や仕事に行くのが憂鬱になるなど、日常生活に大きな支障をもたらします。
腸内フローラの乱れと過敏性腸症候群
過敏性腸症候群を引き起こす原因は、おもにストレスだと考えられています。脳と腸には相関性があるということが研究で分かっており、脳がストレスを感じると腸に伝達されて腹痛などの症状が起こるという仕組みを唱える学者もいます。
お腹の不快感が新たなストレスを呼び、それが脳に伝わって、さらに症状を悪化させます。脳と腸が互いに影響し合うときに、セロトニンという物質が関わっていることも分かっています。セロトニンは、神経伝達物質のひとつです。脳内では精神を安定させる働きがありますが、腸内にも存在します。
腸内のセロトニンは、脳がストレスを感じることで過剰に働き、腸の動きを活性化させて過敏性腸症候群の症状として現れます。ところが、新たな研究では、過敏性腸症候群にはストレスだけでなく腸内フローラの乱れも関係していることが明らかになったのです。健康な人の腸と、過敏性腸症候群の人の腸をそれぞれ調べたところ、過敏性腸症候群の罹患者にはラクトバチルス属とベイロネラ属の腸内細菌が多いという結果が発表されました。
これらの細菌が多いと、腸内で酢酸やプロピオン酸という物質が盛んにつくられて高濃度になり、腹痛などが引き起こされるといわれています。さらに、腸内フローラが乱れることで腸粘膜の細胞同士の間に隙間ができ、そこから異物が侵入して腸粘膜に炎症が起こる点にも注目しましょう。
このような状態をリーキーガット症候群(腸漏れ症候群)と呼び、過敏性腸症候群の原因のひとつと考えられています。
腸内環境を整えることでIBS症状を改善する方法
過敏性腸症候群の改善策としては、薬を使って下痢や便秘、腹痛などを和らげる対症療法が一般的です。また、ストレスを緩和する薬の処方や、心理療法が適用されることもあるでしょう。
腸内フローラと過敏性腸症候群には関連性があることから、腸内環境を整えて過敏性腸症候群の症状を改善する取り組みも注目されています。
食生活の見直し
腸内環境の改善には、発酵食品と食物繊維の摂取量を増やすことが有効です。発酵食品には乳酸菌などの善玉菌が含まれているため、習慣的に食べることで腸内に善玉菌を補給できます。
代表的な発酵食品は、納豆やキムチ、チーズ、味噌、ぬか漬けなどです。食物繊維は、腸内にいる善玉菌のエサとして活用され、善玉菌の数を増やすのに役立ちます。
食物繊維には、水に溶けやすい水溶性食物繊維と、水に溶けにくい不溶性食物繊維があり、善玉菌のエサになるのは水溶性食物繊維です。水溶性食物繊維を含む昆布やわかめ、果物、里芋、こんにゃくなどを摂ると良いでしょう。
プロバイオティクスとプレバイオティクスの活用
プロバイオティクスは、人の体内に摂取すると有益な働きをする生きた菌を指します。納豆菌や乳酸菌などが代表的なもので、ヨーグルトや乳酸菌飲料に含まれる菌もプロバイオティクスです。
プロバイオティクスには、腸内フローラの環境を整えて正常な状態へ導き、過敏性腸症候群を改善する働きが期待されています。それに対してプレバイオティクスは、腸内で善玉菌の増殖を促す難消化性の食品です。
よく知られているのはオリゴ糖で、摂取すると善玉菌のエサとなって増殖を促進し、腸内環境を整えるサポートをします。
生活習慣の改善
腸内環境の改善には、ストレス管理と運動も不可欠です。ストレスは、自律神経の乱れから便秘を引き起こすだけでなく、悪玉菌を増殖させて下痢の原因になります。ストレスを溜めないポイントは、規則正しい生活です。栄養バランスの整った食事や充分な睡眠を心がけ、生活リズムを整えましょう。
また、趣味を楽しむ時間やリラックスして過ごす時間を取り、ストレスを解消することも大切です。腸内環境を改善するために、運動が有効であるという研究報告もあります。
適度な運動をすると、乱れていた自律神経が整い、腸の蠕動運動が正常に近づくといわれています。軽いジョギングやウォーキング程度でも効果が期待できるため、日ごろから運動する習慣をつけましょう。
まとめ
過敏性腸症候群に悩む方は、できる範囲でまずは腸内環境を整えてみてはいかがでしょうか?検査をを見直すヒントとして、腸内細菌叢の状態を調べる腸内フローラ検査がおすすめです。腸内細菌を調べることで、菌のバランスを整えるために必要な食品の種類を詳しく確認できます。キットを使って自宅で検査できるため、過敏性腸症候群でお悩みの人はぜひ検討してみてください。