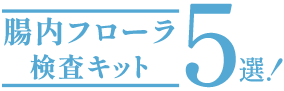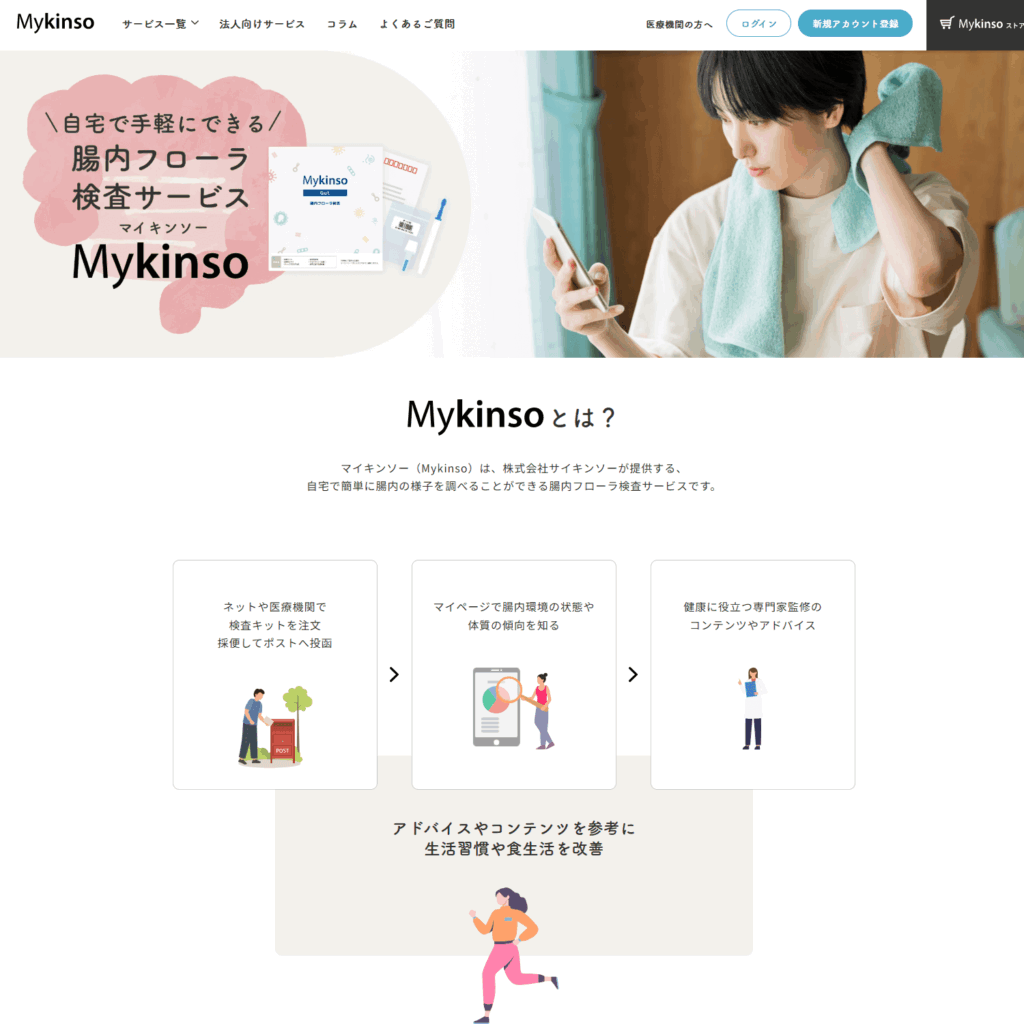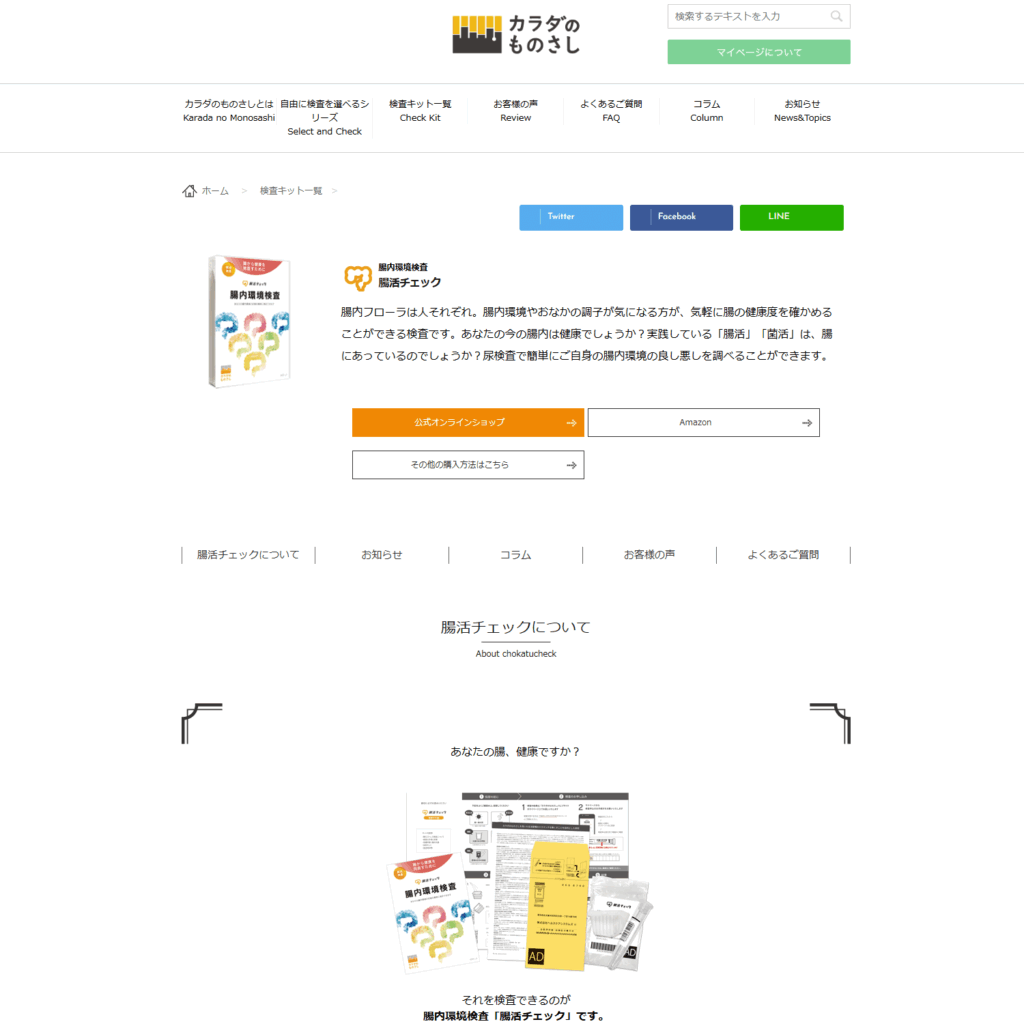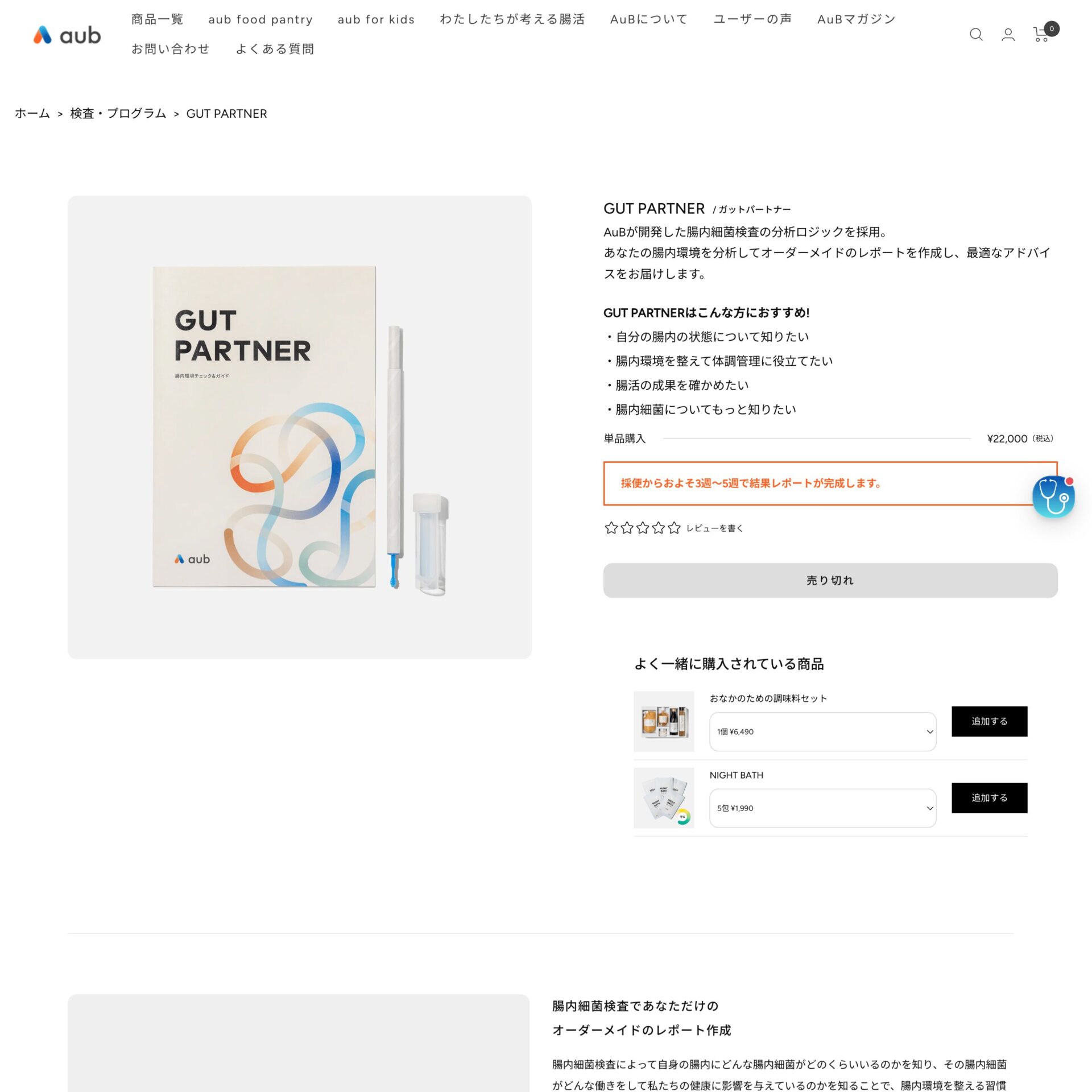「絶食」を意味するファスティングは、腸内環境を整えるのに役立つ可能性があるとして、近年、腸活として注目されている方法です。そこで、この記事ではファスティングの基本的な知識・腸内環境との関係・やり方を紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
CONTENTS
ファスティングとは?その基本と目的
ファスティングとは、食べ物の摂取をルールに従ってコントロールすることです。消化器官に活動しない時間を与えれば、消化するエネルギーが体の回復に利用されると考えられています。食事を控えると、疲労感が軽減する可能性があるのです。
また、ファスティングは食べ物の摂取を一定期間控えて体を回復させたり、体内リズムを整えたりする方法として期待できるのです。
腸内環境の重要性と健康への影響
腸内の状態は、健康にも関係するといわれています。
腸内フローラとは、微生物の種類ごとに集団を作っている状態を指す言葉です。大腸は、腸内フローラ・細菌の代謝物・内臓の分泌物で構成されています。なかでも微生物の影響がとても大きいと考えられており、腸内環境は腸内フローラの状態を指すと認識していいでしょう。
腸内フローラが乱れた状態はディスパイオシスと呼ばれ、あらゆる病気に関連すると考えられています。健康を保つには、腸内フローラを整えてバランスを維持することが大事といえるでしょう。
ファスティングが腸内環境に与える影響
ファスティングは、腸内フローラに影響を与えるといわれています。食事する時間を限定することで、体の中にある不要になったものが外に出やすくなるのです。
腸内の便が排出されれば、微生物の活動も変化すると考えられています。そこで、腸内細菌のバランス・腸内フローラの多様性・腸粘膜の観点から説明します。
腸内細菌のバランス改善
食事を控えると腸内フローラのバランスが変わるといわれています。断食中は腸内の便が出やすくなると考えられているためです。
消化がうまくいかないと、状態の悪い便が作られます。状態の悪い便が体内にあると腸内フローラのバランスが崩れるため、便秘や下痢になると考えられています。
便がきれいに排出されると腸内フローラが変化し、微生物が活動しやすくなるでしょう。断食は、腸内フローラの変化が期待できる方法といえます。
腸内フローラの多様性向上
ファスティングは腸内フローラの多様性を向上させる可能性があります。断食すると、多様な腸内にいる微生物が適切なバランスを保てるようになるでしょう。さまざまな微生物が活発に活動できれば、腸内環境の向上が期待できます。
腸粘膜の修復と炎症の軽減
ファスティングは、腸粘膜の修復と炎症の軽減が期待できます。腸は常に病原菌やウイルスなどが侵入する危険があるため、独自に発達させているのです。腸特有の免疫系を腸管免疫系と呼び、消化する食べ物に近いところから粘液層・上皮層・粘膜固有層に分けられます。
腸内細菌は粘液層に存在し、腸管を保護する作用があるとわかってきました。ファスティングは、腸内の粘液が濃くなり、炎症が軽減する状態に変わると考えられているのです。
ファスティングの種類と腸内環境への効果
ファスティングは断食の期間・周期に分類されます。短期断食・間欠的断食・長期断食が有名です。期待できる効果もそれぞれ異なります。
短期断食(24時間以内)の効果
短期間の断食で有名なのが、16時間ファスティングです。24時間のうち、食事する時間を8時間以内に設定します。1日の食事をすべて8時間以内に済ませましょう。食事する時間帯は自由に設定できます。また、生活のリズムに合わせて食事する時間を12時間まで延長してもいいでしょう。
ファスティングは実施する期間のほかに、準備期間・回復期間が必要です。しかし、16時間ファスティングは準備期間がなくても可能といわれています。16時間ファスティングは、ほかの方法より体の負担が少ないため、実施しやすいといえるでしょう。
間欠的断食の効果
間欠的断食は断食と食事を一定のサイクルで実施するファスティング方法です。カロリーを制限する方法と、断食する方法に分けられます。自分の事情に合わせて選択するといいでしょう。
カロリーを制限する方法では、食事量を減らして生活します。週に5日普通の食事を摂取し、2日間食事量をコントロールするといいでしょう。
断食する方法では、指定した日の食事を控えるのです。断食する日は1週間のうち2日までにするといいでしょう。間欠的断食は、食事量が制限されるため、体重の低下が期待できます。また、計画的に実行するため、規則正しい生活習慣をもつ人や食事管理ができる人に向いているでしょう。
長期断食(3日以上)の効果と注意点
3日以上の長期ファスティングに取り組むと、本格的に脂肪が分解されるでしょう。36~48時間は血液・筋肉にあるグリコーゲンがエネルギー源になるといわれています。そのあと、脂肪を分解し始めると考えられており、脂肪燃焼を目的とする人は長期的なファスティングに取り組むようです。
ただし、長期間の食事制限は体調を崩す危険があり、専門機関への相談が必要とされています。
ファスティングを行う際の注意事項
無理なファスティングは健康を損なう可能性があります。食事を制限するため、さまざまなトラブルにつながることも考える必要があるでしょう。そのため、専門機関のサポートや適切な選択が重要です。具体的には、医師の指導・適切な食事・無理ないスケジュールが必要になるでしょう。とくに、医師の指導は重要です。
医師の指導の重要性
ファスティングは体調に影響が出る場合があるため、医師の指導が重要になります。ファスティングを実施している期間中は食事量が減るため、栄養が不足する可能性があるのです。集中力の低下や疲労感の増大なども考えられます。
また、体調によってはファスティングを控えるべき人もいるでしょう。専門的な知識がある医師の指導に従うことが大切です。
適切な準備食と回復食の選び方
準備期間は具なしの味噌汁が適切といわれています。食事を制限している間は、体内の栄養が使われるため、味噌汁を摂取して補給するとよいでしょう。味にコクがある赤味噌を摂取すると満腹感が得られやすくなります。
また、回復期はおかゆのような消化のいいものを摂取するといいでしょう。
無理のないスケジュール設定
ファスティングは実現可能な範囲でスケジュールを設定しましょう。無理な予定は体調を崩す原因になります。とくに、長期的なファスティングは体に負荷がかかるため、注意が必要です。
また、ファスティング中は空腹を感じるため、大きなストレスを感じるでしょう。ファスティングは無理がないスケジュールに設定するよう心がけましょう。
ファスティング後の腸内環境維持方法
ファスティング後も大切です。腸内環境の状態を維持するには継続的な努力が必要といわれています。腸内細菌をサポートする食品の摂取・バランスのとれた食事習慣・運動とストレス管理に注力しましょう。
プロバイオティクスとプレバイオティクスの摂取
腸内フローラの状態向上と維持にはプロバイオティクスとプレバイオティクスの摂取が重要と考えられています。プロバイオティクスは腸内で活動する微生物を含んだ食品を指します。腸に定着しないため、毎日摂取するといいでしょう。
プレバイオティクスは微生物のエサになる食品を指します。腸内細菌の活動をサポートするものです。食物繊維やオリゴ糖などを含んだ野菜・果物・穀物などが有名です。
この2つを摂取することをシンバイオティクスと呼びます。
バランスのよい食生活の継続
腸内環境を変えるにはバランスのとれた食生活を継続しましょう。腸内フローラの変化には2週間ほどかかるといわれています。そのため、食物繊維を多く含んだ食品や体に有益な微生物を含んだ食べ物を意識して2週間以上続けるといいでしょう。
どちらも途中でやめてしまうと、元の状態に戻るといわれています。
定期的な運動とストレス管理
ファスティング中は体内のたんぱく質が使われるため、筋肉が落ちやすくなると考えられています。適度な運動を取り入れましょう。
また、運動は腸のぜん動運動をサポートする効果があるといわれており、腸の活動が活発になるでしょう。軽いウォーキングやストレッチで体を動かすといいでしょう。
そのほか、腸を刺激するマッサージもおすすめです。マッサージは排便をサポートする効果が期待できます。隙間時間で取り組むといいでしょう。
まとめ
今回はファスティングについて紹介しました。ファスティングは一定の期間食事を控えて胃腸を休ませることを指します。腸内フローラの状態を向上させる可能性があり、近年注目されている方法です。しかし、腸内環境は個人差があるため、正解はありません。そのため、自分の腸内フローラの状態を正確に把握して適切なアドバイスを受けることが重要です。専門の機関で腸内フローラを検査すると、より安心して腸活に取り組めるでしょう。ぜひ、検査を検討してみてください。