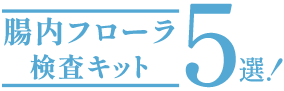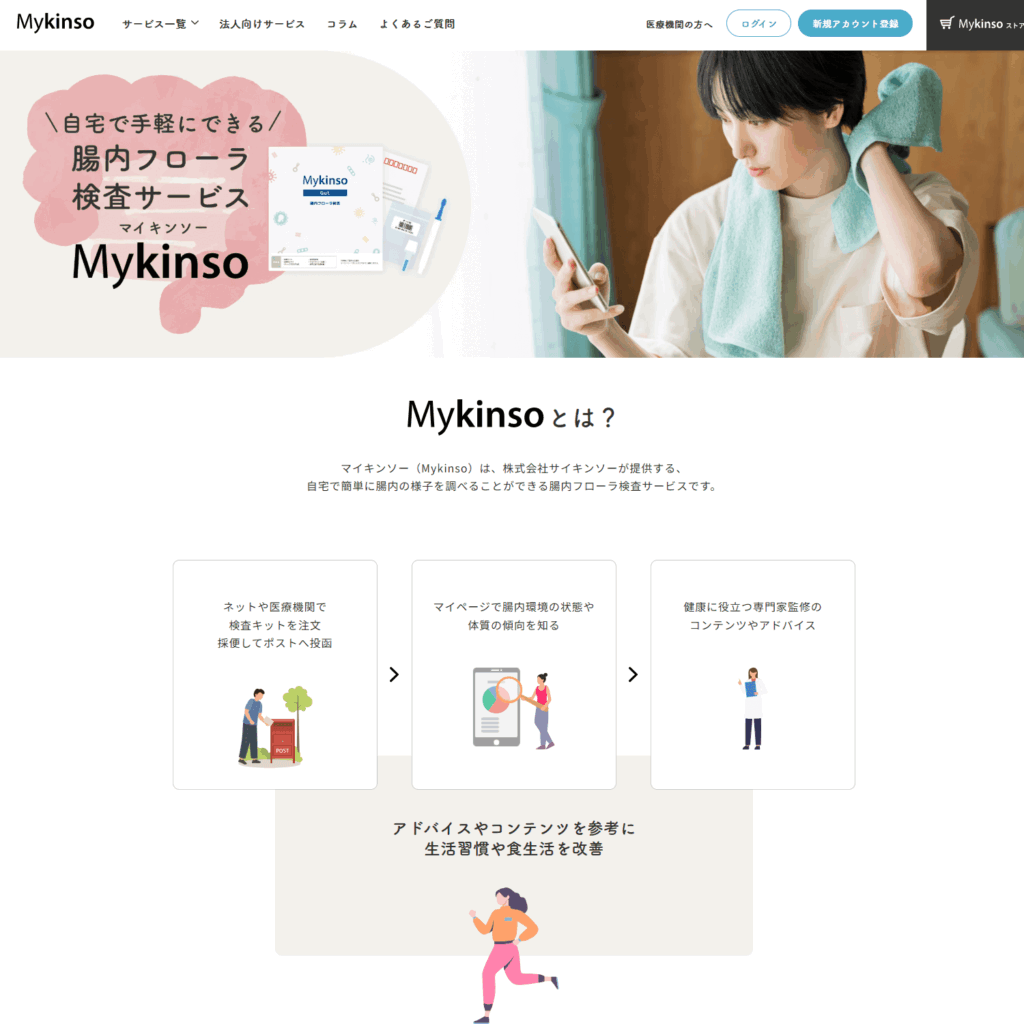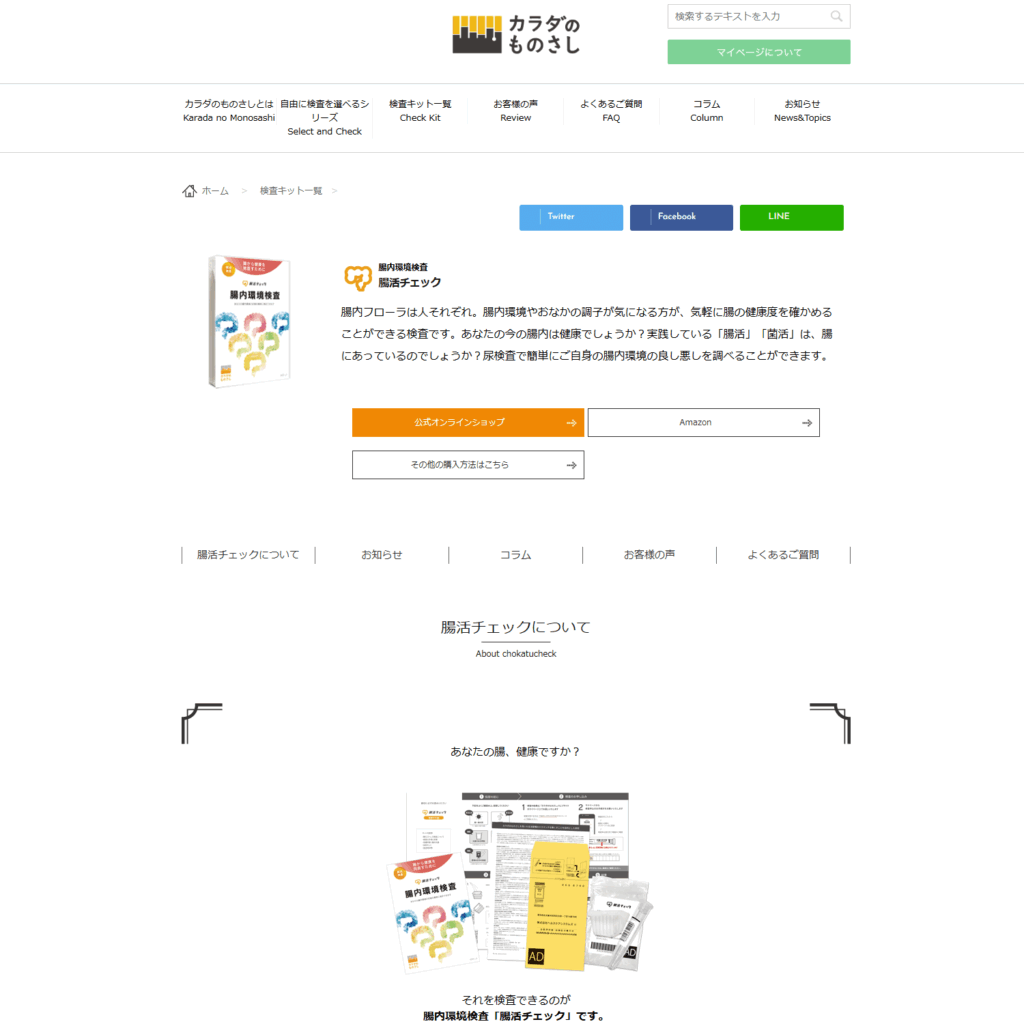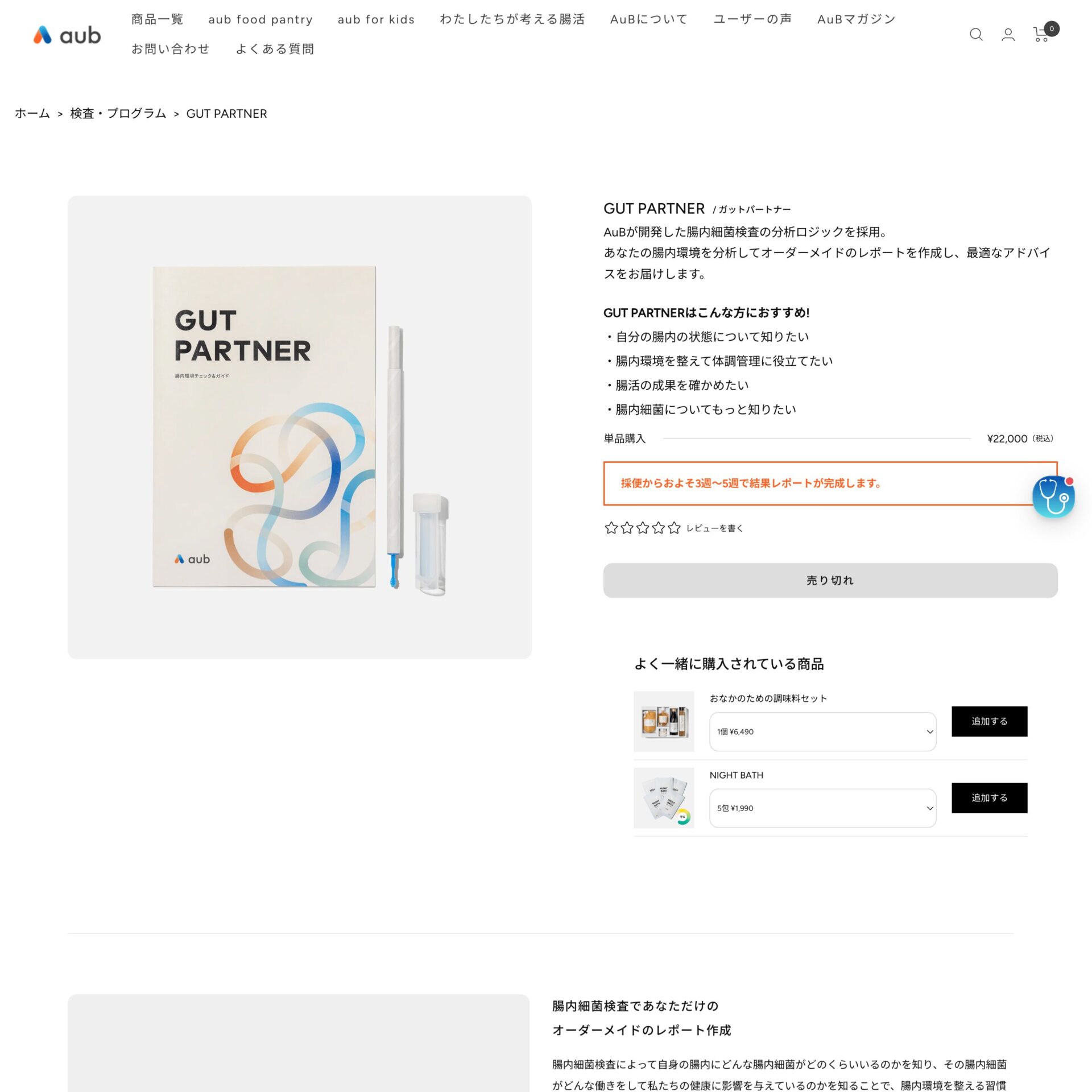便秘や下痢といった消化器症状が続く場合、腸内環境のバランスが崩れている可能性があります。腸内には善玉菌・悪玉菌・日和見菌の3種類の細菌が存在し、これらのバランスが健康維持に重要です。本記事では、腸内細菌の特徴や役割を解説するとともに、腸内環境を整えるための具体的な食事や生活習慣をご紹介します。
CONTENTS
腸内フローラとは?善玉菌・悪玉菌・日和見菌の役割を解説
人の腸内には、1,000種類以上の細菌が、100兆個以上あるといわれています。大腸にある菌は腸内細菌と呼ばれており、主に善玉菌や悪玉菌、日和見菌の3つに分けられます。
これらの細菌には腸内環境を整える働きがあり、その様子がお花畑に似ていることから「腸内フローラ」と呼ばれるようになりました。腸内細菌の構成パターンは一人ひとり異なり、年齢や食生活などの生活習慣が大きく関係しています。
また、腸内細菌がほとんどない状態で生まれてくる赤ちゃんは、母親や離乳食などから細菌をもらい、種類や数を増やしています。腸内フローラの基礎は3歳ごろに決まりますが、その後は食生活などの生活習慣や年齢の影響を受け、変化していくのです。
さらに、腸内細菌である善玉菌・悪玉菌・日和見菌には、それぞれ違う働きがあります。
悪玉菌と善玉菌の役割
善玉菌には、主にビフィズス菌や乳酸菌があり、ビタミンB1、B2、B6、B12、K、葉酸を発生させたり、消化吸収を補助したりする菌です。
また、食物繊維や糖分を使って、乳酸など、身体によい菌を生成します。ただし、善玉菌は腸内に長くとどまることができないため、便とともに排出されてしまう菌です。そのため、腸内環境を整えるためには、善玉菌を接種し続ける必要があります。
悪玉菌にはブドウ菌やウェルシュ菌などがあり、腸内腐敗したり、発がん物質を産生したりする菌です。悪玉菌が増殖すると、毒性のアンモニアやインドールなどの物質が生成され、下痢や便秘、免疫力の低下につながります。
しかし、悪玉菌は体にとって悪い影響を与えるだけではありません。肉類など、タンパク質を分解し、便として排出する働きももっています。そのため、悪玉菌は人間の体には必要不可欠です。大切なことは、悪玉菌を増やしすぎないことです。
日和見菌の役割
日和見菌は、善玉菌と悪玉菌に分類されない腸内細菌で、環境によって働きが変わります。日和見菌は腸内細菌の7割ほどを占めており、善玉菌が優位の状態では、善玉菌の働きをサポートしてくれる菌です。
ただし、悪玉菌が優位の場合は、悪玉菌と同じ働きをするため、腐敗が引き起こされやすくなります。そのため、腸内環境を守るためには、腸内細菌のバランスを整えることが重要なポイントです。
善玉菌・悪玉菌・日和見菌のベストなバランスは、善玉菌が2割:悪玉菌1割:日和見菌7割です。下痢や便秘、体の不調が続いている場合は、悪玉菌の増殖を抑えつつ、善玉菌が多い状態になるよう整える必要があります。
善玉菌と悪玉菌のバランスが健康に与える影響
悪玉菌が増殖すると、腸内フローラのバランスが崩れてしまいます。腸内フローラのバランスが崩れることで、腸の働きが悪くなり、下痢や便秘を引き起こしやすくなります。
さらに、ブドウ球菌やサルモネラ菌などが増殖すると、食中毒を引き起こす可能性が高いです。ブドウ球菌やサルモネラ菌は悪玉菌の一種で、腸内にある食べ物を腐敗させてしまいます。
腸内で悪玉菌が増えると、内臓に負担がかかったり、老化を促進させたりします。また、これらは大きな病気にもつながるため、注意が必要です。
しかし、悪玉菌は体に悪影響を与えるだけではありません。悪玉菌がないと、善玉菌が働かず、食べ物の消化や吸収がしにくくなります。そのため、悪玉菌も人の体には必要な腸内細菌です。しかし、増えすぎると体に悪い影響を与えるため、善玉菌とのバランスが大切です。
悪玉菌が増殖する原因は、主に食生活の乱れやストレス、運動不足です。さらに、加齢も原因として考えられています。そのほかには、便秘や細菌感染も原因のひとつです。
そのため、悪玉菌が増えすぎないように対策が必要です。加齢によって悪玉菌が増殖することは防げませんが、そのほかの原因は、食生活や睡眠などの生活リズムを意識することで予防可能です。
腸内フローラのバランスを整える食事を意識したり、適度な運動を取り入れたりすることが大切です。便秘や下痢などの消化器症状が気になる方は、腸内環境を整えるための食事を摂ったり、生活リズムを見直したりしましょう。
また、腸内細菌の数をチェックすることは難しいですが、便や体調で腸内環境をなんとなくでも把握しておきましょう。
腸内環境を整えるための食生活のポイント
腸内環境のバランスが崩れても、食生活を見直すことで改善が目指せます。腸内環境を整えるためには、発酵食品の摂取や食物繊維を効果的に摂ることが重要なポイントです。
加齢による腸内環境の乱れは防げませんが、食生活が原因の場合は予防・改善が期待できます。ここでは、腸内環境を整えるための食生活のポイントを紹介します。
下痢や便秘、体の不調が続いている方は、ぜひ参考にしてみてください。
発酵食品の摂取で善玉菌を増やそう
悪玉菌が増殖すると腸内環境が乱れるため、バランスをよくするためには、善玉菌を増やす工夫が必要です。たとえば、善玉菌が多く含まれている食品を積極的に摂取することで、腸内環境が整えられるでしょう。
善玉菌が多く含まれている食材は、主にヨーグルトや乳酸飲料、納豆などの発酵食品です。肉類は悪玉菌が増える原因になるため、発酵食品も一緒に摂取するのがおすすめです。
また、甘酒やぬか漬けなども、善玉菌を増やす働きがあります。
そのほか、プロバイオティクスを意識することも重要です。プロバイオティクスとは、生きている微生物で、乳酸菌やビフィズス菌などがあります。また、食材だけでなく、サプリメントでの摂取もおすすめです。ただし、腸内環境を整えるために、発酵食品を摂取するときは、ほかの栄養素も一緒に摂れるように工夫してみましょう。
肉類は悪玉菌が増える原因の食材ですが、悪玉菌がまったくないと腸内環境が悪くなってしまいます。摂取する栄養素に偏りがないよう、バランスよい食事を摂ることも重要なポイントのひとつです。
食材だけでの摂取が難しい場合は、サプリメントや医薬品などを使って摂取するよう心がけましょう。また、医薬部外品の整腸剤も有効です。整腸剤は、便秘や下痢など、消化器症状の改善に役立ちます。
バランスのよい食事を意識するとともに、サプリメントや医薬品なども服用して善玉菌を増やしましょう。
食物繊維の重要性と効果的な摂り方
腸内環境を整えるためには、善玉菌を増やすだけでなく、食物繊維や摂り方も大切なポイントです。食物繊維は善玉菌のエサとなるため、発酵食品と一緒に摂取するとよいでしょう。
食物繊維が含まれている食材は、主にきのこ類や穀類です。また、同じ穀類でも、白米に比べると玄米は食物繊維がより豊富に含まれています。
さらに、食物繊維は大腸の中にある便のかさを増やす働きもあり、便秘の改善効果も期待できます。便秘が改善されると、悪玉菌が発生しにくい環境が作れるでしょう。
また、発酵食品や食物繊維が含まれている食材を摂るときは、食べ方にもポイントがあります。善玉菌を摂取しても、腸まで届かなければ腸内環境の改善が目指せません。
そのため、善玉菌を増やすために食生活を見直す際は、効果的な摂り方を意識することも大切です。たとえば、食事の前に水分を摂ると、腸のぜん動運動が活発になるため、消化・吸収しやすくなります。
消化・吸収しやすくするためには、しっかり噛んでゆっくり食べて、副交感神経を優位にすることも重要です。また、夕食は就寝の1〜2時間前に済ませるよう意識することも大切です。
胃で消化されていない食べ物が残ったまま就寝すると、腸内環境の悪化につながります。腸内環境を整えるためには、食生活だけでなく、生活習慣の見直しも必要です。
不規則な生活をしている方は、夕食の時間や就寝時間を決めることで、健康的な生活が送れます。また、腸内環境を整えるためには、健康的な生活や食事が欠かせません。
食事を摂るときは、食物繊維が含まれている穀類や芋類、野菜を選び、食べ方も意識しましょう。さらに、副交感神経を優位にさせるストレッチもおすすめです。
生活習慣の改善で腸内フローラを健全に保つ
腸内環境を整え、腸内フローラを健全に保つためには、生活習慣の改善も欠かせません。ストレスの蓄積や乱れた睡眠、運動不足は腸内環境が悪くなる原因です。
腸内環境は、自律神経とも深い関わりがあるため、生活習慣を改善して整えることが大切です。ここでは、改善するべき生活習慣を紹介します。
適度な運動とストレス管理の方法
適度な運動は、腸内環境を整えるためにとても重要です。運動不足が続くと、自律神経が乱れてしまい、腸内環境も悪くなっていきます。自律神経には、体や心を活動的にする交感神経とリラックスさせる副交感神経の2つがバランスをとっています。
自律神経の乱れは、便秘や下痢などを引き起こす原因のひとつです。また、腸の動きを活発にするためには、副交感神経を優位にする必要があります。
適度な運動は副交感神経を優位にさせるため、腸内フローラを健全に保つために必要です。運動不足を感じている方は、日々の生活に運動を取り入れるよう意識してみましょう。
いきなり激しい運動を始めるのではなく、ウォーキングや軽いジョギングから始めるのがおすすめです。また、腸内環境を整えるためには、ストレッチやエクササイズも有効です。仰向けの状態でできるものや椅子に座ってできるものなどがあります。ウォーキングや軽いジョギングの継続が難しい場合は、これらのストレッチやエクササイズを取り入れましょう。
また、ストレスの蓄積も腸内環境を悪化させる原因です。人の脳や腸は、神経を通じて情報交換・伝達しており、お互いに影響をおよぼし合います。
これを脳腸相関といい、ストレスは腸にも大きな影響を与えます。ストレスが蓄積されると、脳腸相関によって腸にも影響がおよび、便秘や下痢などの消化器症状が起きやすいです。
腸内フローラを健全に保つためには、ストレスを溜めない工夫が必要です。自分に合った方法でストレス発散し、腸内フローラを健全に保ちましょう。
また、ストレスを発散すると善玉菌の働きを後押しする効果も期待できます。さらに、質のよい睡眠にもつながるため、ストレスを感じている方は自分の好きな方法で解消させてみてください。
規則正しい生活リズムの重要性
腸内フローラの健全を保つためには、規則正しい生活リズムがとても重要です。良質な睡眠を取るなど、規則正しい生活を送ることで、腸内環境の改善が目指せます。
生活習慣の乱れは、悪玉菌が増える原因のひとつです。たとえば、睡眠時間が短くなると、腸内環境のバランスが乱れるといった研究結果もあります。
また、質のよい睡眠も腸内環境のバランスに大きな影響を与えます。腸内環境を整えて、腸内フローラを健全に保つために、以下の生活リズムを意識してみましょう。
・毎日同じ時間に起床・就寝する
・朝起きたらカーテンを開けて朝日を浴びる
・就寝前はスマホやテレビなどの強い光を見ない
・就寝前はカフェイン・アルコールの摂取や喫煙を避ける
毎日同じ時間に起床・就寝することで、生活リズムが整います。また、朝起きたときにカーテンを開けて朝日を浴びることで、セロトニンの分泌量が増えて、ストレスが軽減されたり、リラックス効果が得られたりします。
就寝前のスマホやテレビは、脳が覚醒してしまうため、睡眠の質が悪くなりやすいです。また、就寝前にカフェインやアルコールを摂取したり、喫煙したりすると、睡眠サイクルが乱れるため、睡眠の質が悪くなります。
腸内環境を整えるためには、食生活だけでなく、規則正しい生活リズムを意識することも重要です。就寝時間が遅かったり、睡眠時間がバラバラだったり、不規則な生活をしている方は、正しいリズムに戻せるように意識してみましょう。
規則正しい生活リズムになれば、ストレスも軽減され、心身の健康につながります。
腸内フローラのバランスをチェックする方法
腸内フローラのバランスは、便の形・におい・頻度からある程度はチェックできます。腸内フローラのバランスが気になる方は、便を観察してみてください。
腸内フローラのバランスが整っていると、表面が滑らかでソーセージのような状態の便が出ます。硬くてコロコロしていたり、液状で柔らかかったりする便が出ている場合は、腸内フローラのバランスが崩れている可能性が高いです。
硬すぎず、柔らかすぎないソーセージ上の便が出るようになれば、腸内フローラが整っているといえます。反対に、コロコロしていたり、ソーセージ状でも硬かったりする場合は、腸内環境を整える必要があります。
また、便のにおいを確認することも、腸内フローラのバランスがチェックできる方法のひとつです。腸内フローラのバランスが整っているとき、便のにおいはそれほど強くありません。
しかし、腸内フローラのバランスが崩れて悪玉菌が多く発生していると、便のにおいが強くなります。また、肉類中心の食生活が続いていると、悪玉菌の働きが活発になるため、便だけでなくガスのにおいも強くなるでしょう。
便やガスのにおいが強いと感じたら、食生活を見直すことが大切です。便の出る頻度も、腸内フローラのバランスをチェックするポイントです。
1週間に3回以上便が出ていれば、腸内フローラのバランスがよいといえます。ただし、毎日便が出ていても、強くいきまないとでなかったり、残便感があったりすると、原因として腸内フローラのバランスが崩れていることが考えられます。
便を観察すると、硬さやにおい、頻度から、腸内フローラのバランスが確認できます。硬い便や柔らかすぎる便が続いたり、強いにおいがしたりする場合は、食生活や生活習慣を見直しましょう。
まとめ
人間の大腸にある菌は腸内細菌と呼ばれており、主に善玉菌・悪玉菌・日和見菌の3つに分けられます。善玉菌は体によい菌を生成するため、重要な腸内細菌です。善玉菌にはブドウ菌やウェルシュ菌など、食べ物を腐敗させる菌があるため、増えすぎると体に悪い影響を与えます。しかし、悪玉菌がまったくないと、タンパク質を分解し、便として排出する働きもあります。そのため、悪玉菌を完全に無くす必要はありません。腸内環境を整えるためには、善玉菌や悪玉菌などのバランスが大切です。便の形やにおい、頻度から腸内環境をチェックして、不安な点があれば腸内検査キットの使用を検討してみてください。あなたの腸内環境が詳細に分かりますので、それを基に改善に努めてください。