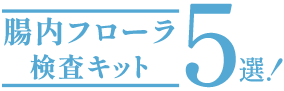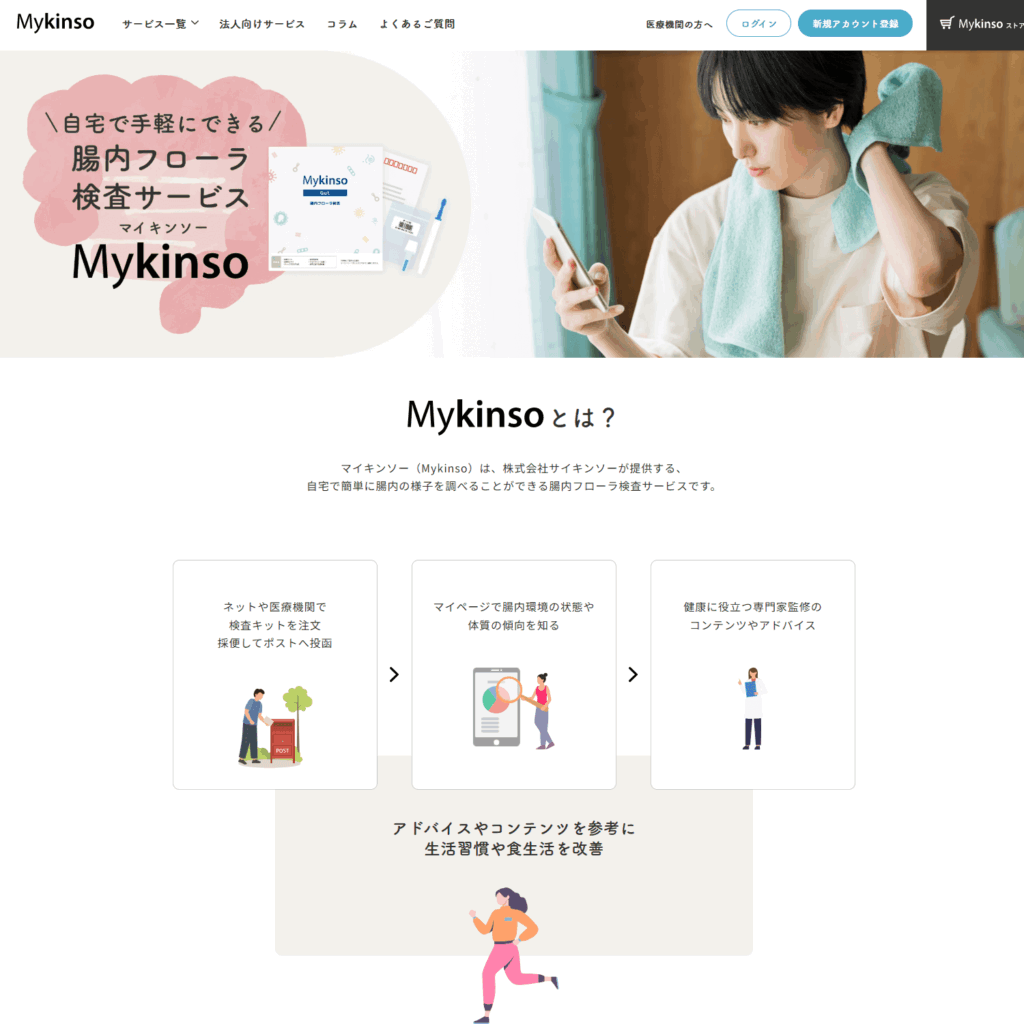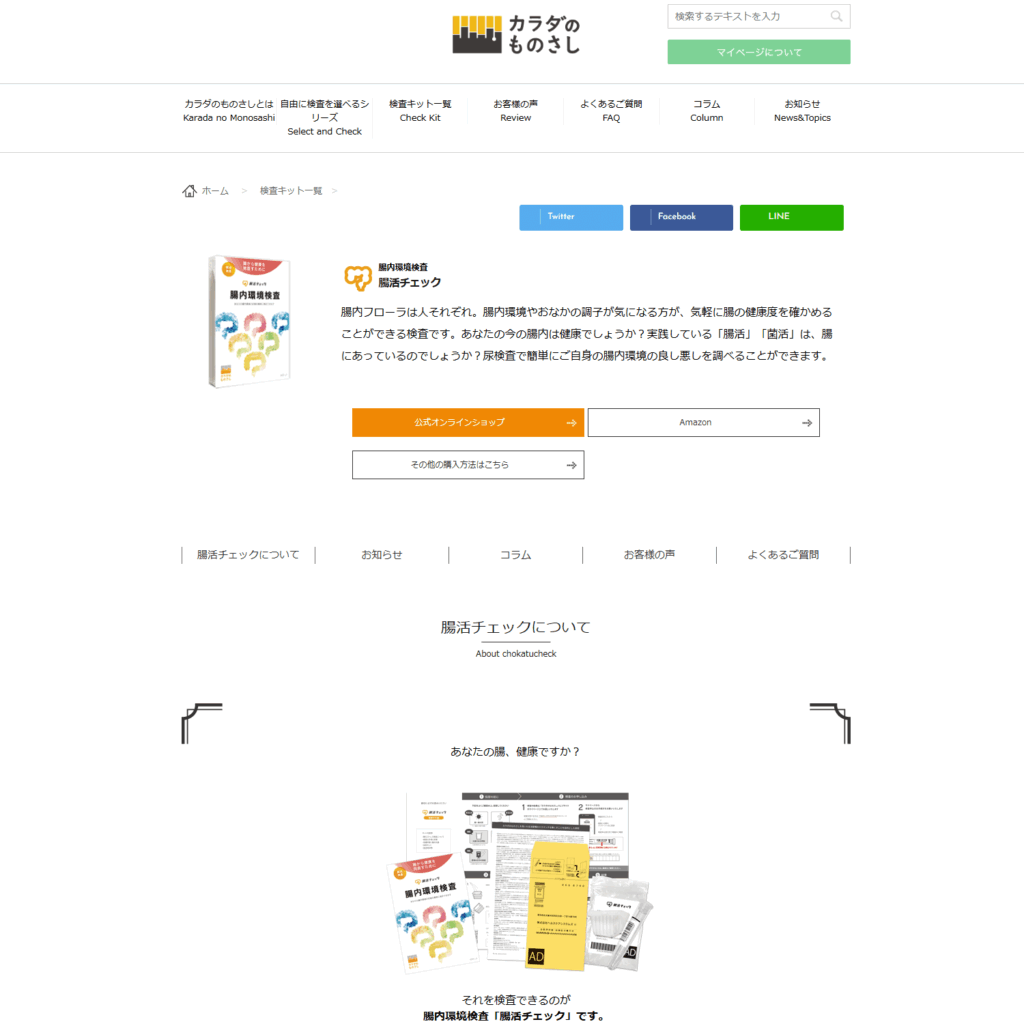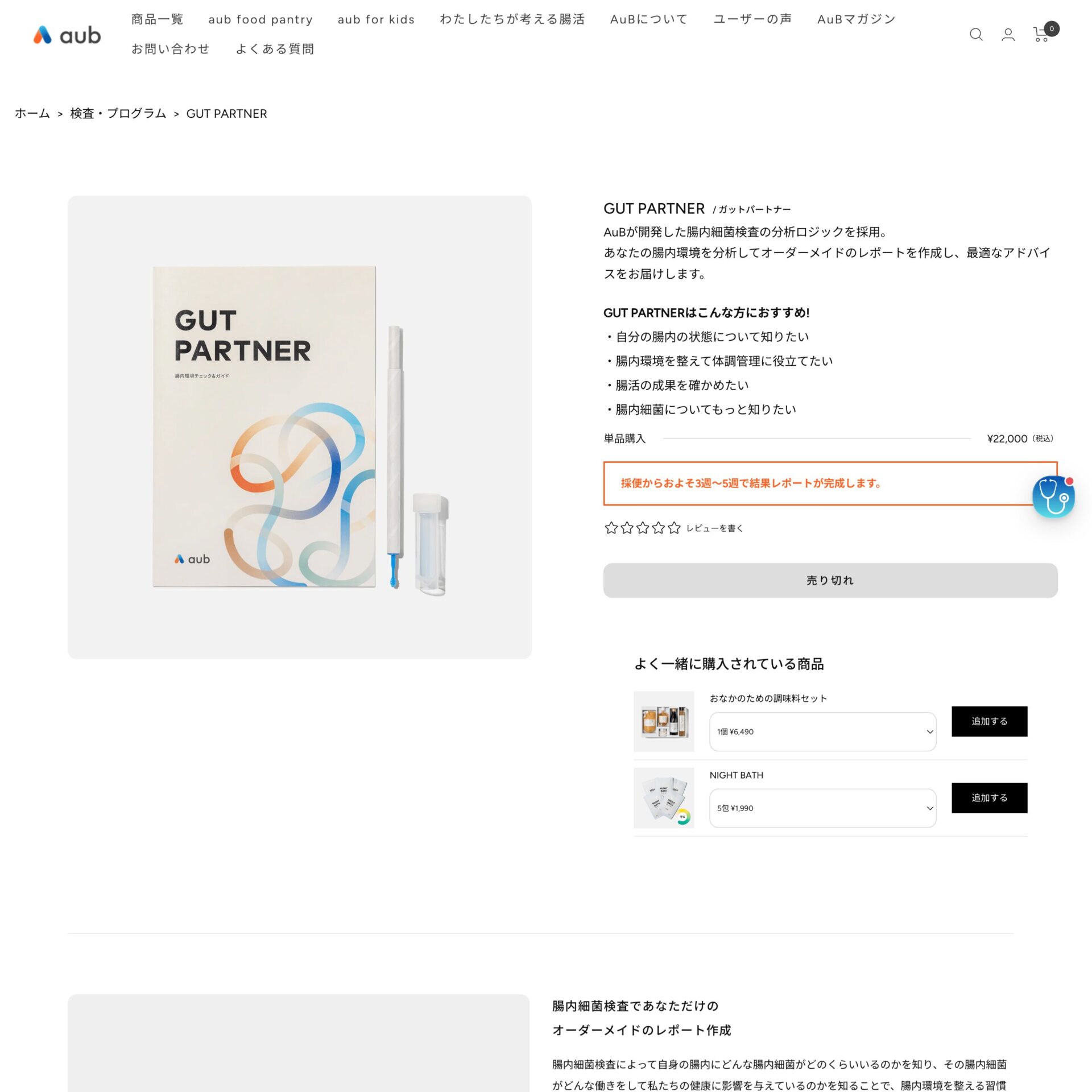腸内の環境とメンタルヘルスは関係があると考えられています。近年では腸によるメンタルの安定に注目が集まっているのです。そこで、この記事では、腸内環境とメンタルの関係、腸内環境が向上するといわれる方法を紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
CONTENTS
腸内環境とうつ病の関係とは?
腸内環境は人の気分に関係している可能性があります。人のメンタルは神経伝達物質でコントロールされていると考えられており、その生産量が多い腸が注目されているのです。
メンタルの不調にうつ病があります。うつ病とは、慢性的な悲しみや無力感などの特徴があり、多くの人がかかる可能性があるものです。
普通の悲しみの場合は、数日もすると少しずつ前向きな気持ちになるでしょう。しかし、うつ病の症状は何週間も続くといわれています。日常生活に影響する場合もあるのです。うつ病の原因のひとつは、神経伝達物質のバランスが崩れることだといわれています。
そうした神経伝達物質と関係が深いといわれる、腸内細菌とメンタル・セロトニンと腸内細菌について説明します。
腸内細菌がメンタルヘルスに与える影響
腸内にいる細菌は神経伝達物質の生産に関与していると考えられています。腸内細菌のバランスが崩れると、腸内に炎症が起きて神経伝達物質の生産に影響し、メンタルが不安定になるといわれています。腸内細菌のバランスが崩れると、メンタルに作用する可能性があるといわれるのはこのためです。
腸内細菌とメンタルの研究は難しく、現在も研究されている分野のため、今後の研究によってより詳しく解明されるでしょう。
セロトニンと腸内環境の関連性
セロトニンとは精神を安定させる作用があると考えられているホルモンです。幸せホルモンとも呼ばれています。体内にあるセロトニンの多くが、腸内で生産されており、腸の状態と関係していると考えられているのです。そのため、腸内環境のバランスが崩れてセロトニンの生産量が変動すると、メンタルに影響する可能性があります。
腸内環境の乱れが引き起こすメンタル不調
ここまでの説明にあるように、腸内環境とメンタルの関係性が深いのは、メンタルに関係している物質を腸内で生産しているためです。腸内環境の良し悪しは腸内細菌の影響が大きいといわれており、微生物とメンタルの関係を知る必要があるでしょう。
そこで、腸内フローラと精神状態・腸内環境の悪化とうつ症状について解説します。
腸内フローラのバランスと精神状態の関係
腸内細菌が、種類ごとに集団で活動している様子を腸内フローラと呼びます。腸内細菌は腸内にいる微生物、腸内フローラは微生物の種類ごとに分かれている状態を指す言葉です。
腸内フローラのバランスが精神状態に関係している可能性があります。40種類ほどの神経伝達物質が腸内で生産されているといわれているためです。
気分を安定させる作用があるとされるセロトニンの多くは腸内で作られているという説があるように、精神状態に深く関係しているといわれる腸内フローラですが、その状態は人によって違い、まずは自分の状態を知っておくことが重要です。
腸内環境の悪化がもたらすうつ症状
うつ病は神経伝達物質のバランスが関係しているという考えがあり、腸内環境が乱れることで生産が減り気分が不安定になるといわれています。中でもセロトニンはうつ症状と深く関係しているとされています。セロトニンの生産が多い腸内の環境は重要といえるでしょう。
精神的なストレスで下痢や便秘になる方も多いと思いますが、メンタルの状態が悪循環に陥るおそれがあるため注意が必要です。
腸活でうつ病を予防・改善する方法
腸活でうつ病の予防や状態の向上が期待できます。腸とメンタルは深く関係していると考えられているためです。発酵食品の摂取・食物繊維の摂取・生活習慣の見直しで腸内環境の調和を目指すといいでしょう。ただし、腸内環境は人によって異なります。自分の状態を正確に把握して適切なアドバイスを受けるといいでしょう。
発酵食品の摂取とその効果
発酵食品を摂取すると、腸内環境を整える微生物を取り入れられるといわれています。また、微生物が生産した物質の吸収も期待できるでしょう。
納豆や味噌などは手軽に食べられるため、継続しやすいでしょう。また、長い伝統の中で発展してきた発酵食品は日本人の腸内に適切といわれています。
そのため、発酵食品を上手に活用することで、腸内フローラの状態が向上する可能性があります。
食物繊維の重要性と摂取方法
食物繊維は腸内フローラのバランスを保つために重要といえるでしょう。微生物の活動をサポートする役割があると考えられています。とくに、水溶性の食物繊維は発酵しやすい性質があり、発酵過程で腸内細菌のエサになる物質が生産されるため、腸内環境の向上に適切とされているのです。
生活習慣の見直しで腸内環境を整える
腸内環境を変えるには習慣を考え直す必要があるでしょう。生活習慣を整えることで、腸内環境はキープされやすくなります。まずはバランスのよい食事を決まった時間に摂取するといいでしょう。
また、嗜好品を控える行為も腸内環境を保つために重要といわれています。微生物の活動を邪魔する可能性があるためです。過剰な摂取を控えるようにするといいでしょう。腸内環境を保つには、バランスのよい食事と嗜好品のコントロールが重要といえます。
そのほか、運動と睡眠も見直すといいでしょう。運動は腸のぜん動運動をサポートすると考えられており、排泄が期待できるのです。睡眠も腸内環境に関係しているといわれています。睡眠の質がよくなれば、腸内環境の状態も変化するでしょう。
腸内環境を整える具体的な食事法
腸内環境を整えるには、発酵食品を意識的に摂取するといいでしょう。発酵食品はどこでも買える品目が多く、習慣として取り入れやすいといわれています。バランスのいい食事をベースにして、無理ない範囲で発酵食品を摂取しましょう。なお、腸内環境には個人差があるため、専門的な機関で調べてもらうといいでしょう。
おすすめの発酵食品とその摂取量
おすすめの発酵食品は、ヨーグルト、納豆、味噌です。ヨーグルトの摂取量は、一般的には1日100gがよいといわれています。納豆の場合は1日1パック、味噌は1日1杯が目安とされています。
ただし、味噌は塩分を含んでいるため、体調に不安がある人は専門機関に相談してから摂取するといいでしょう。
バランスのよい食事で腸内フローラをサポート
バランスのよい食事は腸内フローラをサポートするといわれています。腸内環境は、たくさんの微生物が関わっていると考えられているからです。摂取する食品が多くなることで微生物の種類や活動にもよい影響があると考えられています。
主食・主菜・副菜などのかたよりがない食事がいいでしょう。また、1日3食定まった時間に食事すると腸内環境のバランスがよくなるとされています。
腸内環境改善によるメンタルヘルスの向上事例
腸内環境が変化するとメンタルにも影響すると考えられています。事例を分析するとわかりやすいでしょう。うつ病患者のケーススタディと専門家が語る腸内環境とメンタルの関係を説明します。
腸活で改善したうつ病患者のケーススタディ
近年では、ストレスに対処する力と腸内細菌は関係していると考えられています。そのため、腸にフォーカスした研究が進められているのです。
一般成人を対象とした研究で発酵食品を30日間摂取したケースでは、摂取していない被験者と比べて気分の落ち込みや不安が軽減した可能性があるとされています。ただし、腸内環境とうつ病の分野についての研究は発展途上です。今後の研究報告に期待されています。
専門家が語る腸内環境とメンタルの関係
腸内環境の専門家の中には、腸と脳の関係を腸脳相関と呼び、お互い影響していると考えている人もいます。そのため、うつ病に限らず精神的な不調に関係するといわれています。ただし、事例が少ないため、さらにエビデンスを蓄積する必要があるでしょう。今後の研究に注目しています。
まとめ
今回は腸内環境とメンタルの関係について紹介しました。近年では腸内フローラと人の気分には関係があるといわれていることもあり、腸内フローラの状態に注目が集まっているのです。しかし、腸内の環境は人によって異なるため、明確な正解はありません。自分の状態を把握してアプローチする必要があるでしょう。腸内の状態を把握する方法として、腸内検査があります。検査の結果、適切なアドバイスを受けることで状態の向上が期待できます。自分の腸内環境が気になる方はぜひ検査を検討してみてください。